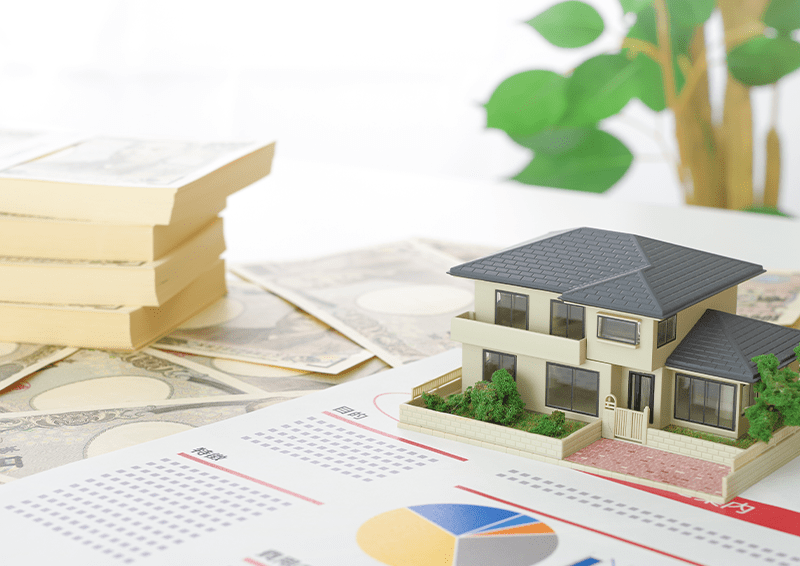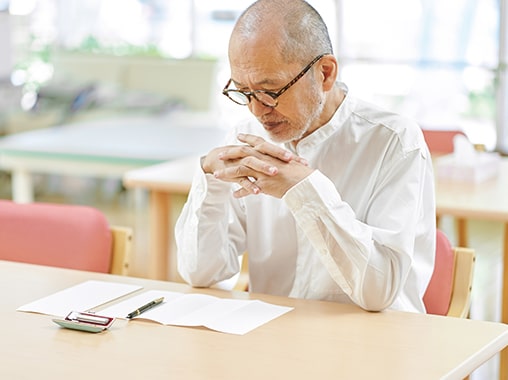相続税の基礎控除額は「相続人の数」で変わる?

- 相続税申告
- 相続ワンポイントメモ
基礎控除額とは、相続税を計算する際に「相続財産から控除できる額」、
つまり 財産額がいくらまでなら相続税がかかってこない という金額です。
基礎控除の金額は、一律で決まっているのではなく、相続が開始するごとに計算します。
相続税の基礎控除額は法定相続人の数で異なる
相続税の基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※『法定相続人』とは、民法で定められた「相続の権利を持つ人」を指します。
相続人の家族構成で変わる基礎控除の事例を紹介
基礎控除の計算を具体例に沿って確認してみましょう。
父・母・子供2人の4人家族
両親と子ども2人の4人家族で、父親が亡くなった場合では、相続人は母親と子ども2人の計3人です。したがって、基礎控除の金額は、以下の通りです。
3000万円 + ( 600万円 × 3名 ) = 4800万円
基礎控除額は4800万円となり、 父親の相続財産が5000万あった場合、
5000万円 - 4800万円 = 200万円 に相続税がかかってくる、ということになります。
孫養子がいた場合
両親と子ども2人の4人家族で、孫1人を養子とし、父親が亡くなった場合はどうでしょうか。
法定相続人は母親と子ども2人、孫養子1人の計4人です。
3,000万円 + ( 600万円 × 4人 ) = 5,400万円
当然、法定相続人の人数が多い程、相続財産から控除できる「基礎控除額」は大きくなりますが、
代襲相続(子が先に亡くなっている場合、孫が相続人になること)以外では孫の相続税は2割加算となるため注意が必要です。
被相続人の配偶者が妊娠中の場合
亡くなった方の配偶者が妊娠中の場合、お腹の中の胎児も相続人となります。
民法では「胎児は相続についてすでに生まれたものとみなす」と規定されています。
もしも相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに出生しない見込みの場合は胎児がいないものとして相続税を申告し、出生した後に、出生日の翌日から4カ月以内に、修正申告または更正の手続きを行います。
税制改正で相続税がかかってくる相続が増加
基礎控除の金額は2013年の税制改正により、2015年1月1日以後の相続から4割減額されました。
改正以前は 5000万円+(1000万円×法定相続人の数) という計算式だったため、
相続財産から控除できる金額が大きかったのですが、改正後は大幅に控除額が減額されたため相続税がかかる相続が増えることとなりました。
つまり、誰しも相続税がかかってくる可能性が高まったため、より生前対策について考えておくのが大切になってきます。
今後も法改正によって基礎控除の金額が変更される可能性もあるため、試算をする際には最新の情報を得るようにしましょう。
相続税がかかるのか掛からないのか、またかかるとしたらどのくらいの税額なのかを事前に把握しておくだけでもご家族は安心できるのではないでしょうか。