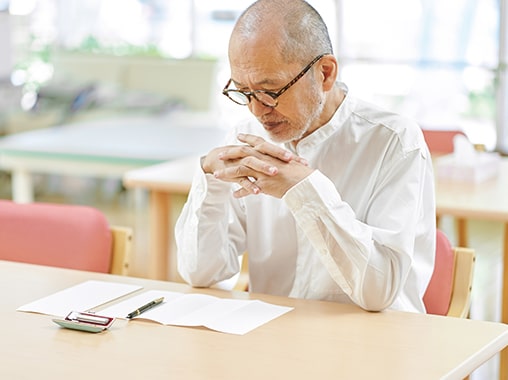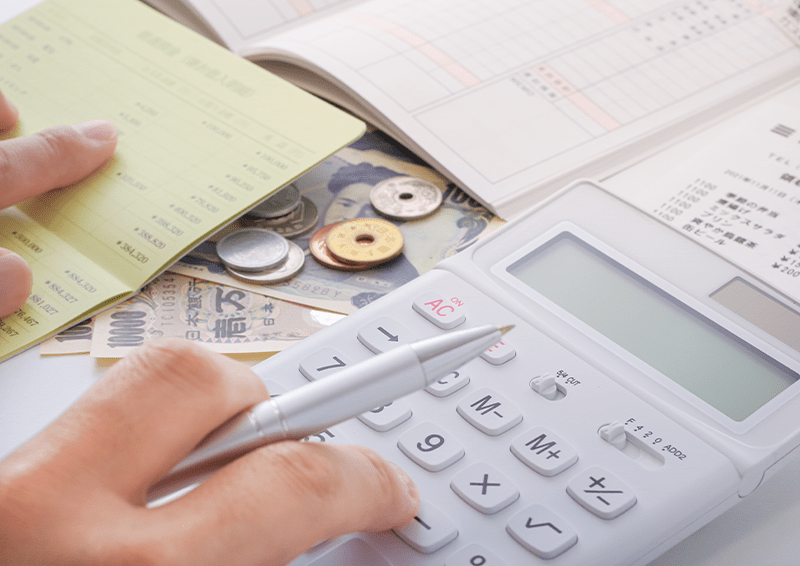
相続手続の中で一番大変なのが、遺産分割です。財産目録を作成し、被相続人の財産がすべて判明した後、それを相続人同士でどのような分割にするかを話し合う必要がありますが、中にはここで手続が止まってしまうケースもあります。その原因は親族間での争いです。相談に来られる方の中でもよく、「遺産が多いと揉めるかもしれないけど、うちは大丈夫」と言われる方がいますが、そうとは限りません。預貯金があまり無く、自宅のみが財産という場合も分割方法で揉める場合がありますし、相続人が遺留分を請求するといったケースもあります。
遺産分割の課題
相続が発生すると、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議は、相続人全員の合意が必要であり、合意内容を文書化した「遺産分割協議書」を作成することで、初めて法的な効力を持ちます。しかし、実際には以下のような課題が生じることがあります。
相続人同士で意見が合わない
兄弟姉妹でそれぞれ生活状況が異なる場合や、故人との関係性に温度差があると、「誰がどれだけ相続するか」で揉めてしまうことがあります。
「長男だから多めにほしい」「介護をしてきたのは自分だ」など、それぞれの立場からの主張がぶつかり合い、感情的な対立になりがちです。
相続財産の内容がわかりにくい
故人の遺産の全体像が不明確であると、話し合いの前提がそろわず、協議が進みません。不動産が複数あったり、有価証券やネット銀行など見落としがちな財産がある場合、正確な把握ができていないと「損をした」「隠しているのでは」といった疑念を生むこともあります。
分割方法が難しい財産がある
不動産や株式など、物理的に分けにくい資産をどう配分するかは大きな争点になります。たとえば「親の家を誰が相続するか」「売却して分けるのか、そのまま住み続けるのか」など、感情的な要素もからみ、合意形成が難しくなりがちです。
相続人の一部が遠方または疎遠で連絡がとりづらい
相続人が海外や地方に住んでいたり、普段から交流がない場合、連絡手段が限られ協議自体が始められないこともあります。こうした場合、専門家の第三者的な介入が必要となることがあります。
協議書の作成に不安がある
せっかく話し合いがまとまっても、「遺産分割協議書」が法的に正しく作られていなければ、後から手続きが無効になる恐れもあります。登記や銀行の名義変更など、各手続きに対応する正確な形式での作成が求められます。
遺産分割の手続き
遺産分割の方法は、通常遺言があればそれに基づいて行います。遺言が無い場合は、基本的に話し合いで決めてもらいます。話し合いの際の目安となるのが、法定相続分です。例えば、話し合いで揉めて、家庭裁判所での審判、あるいは裁判となる場合、最終的には法定相続分で分けるケースが多くなります。
相続財産の調査・評価
預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の内容を明確にし、適切な評価を行います。
相続人間の調整支援
相続人同士の意見調整をサポートし、円滑な協議が進むように支援します。
遺産分割協議書の作成
法的に有効な遺産分割協議書を作成し、必要に応じて専門家と連携します。
専門家との連携
税理士、司法書士、弁護士などの専門家と連携し、相続税申告や登記手続きなども一括してサポートします。
まとめ
遺産分割をする際、重要なポイントが2つあります。
一つは税金が安くなるよう分割するという点です。ただし、いくら税金が一番安くなるよう分けたといっても、必ずしもすべての相続人が納得する訳ではありません。税金を安くするために分割方法で揉めて、数十年争っているといったケースもあります。
そのため、二つ目のポイントが円満に分割するという点です。この二つの視点で遺産分割を行うことが重要です。