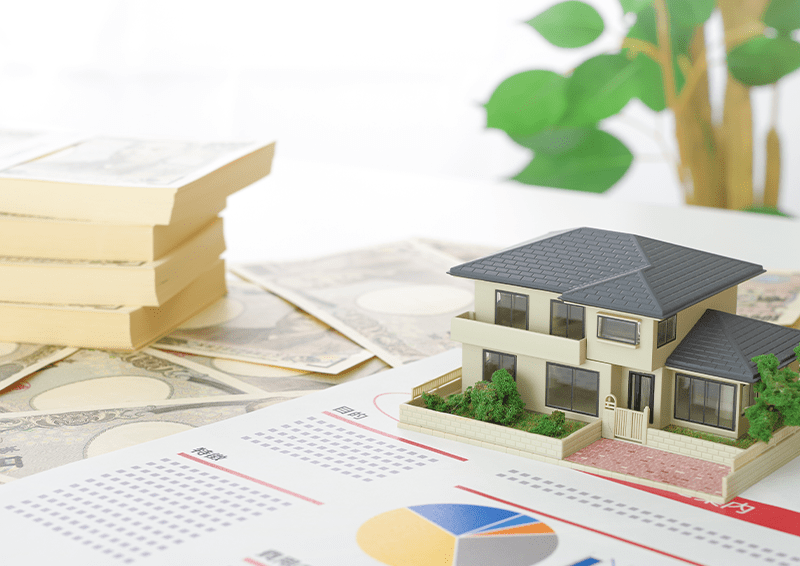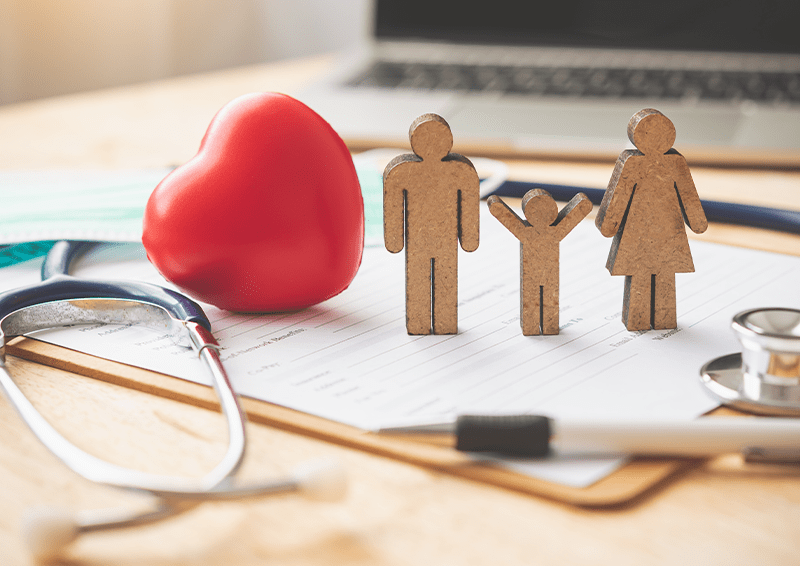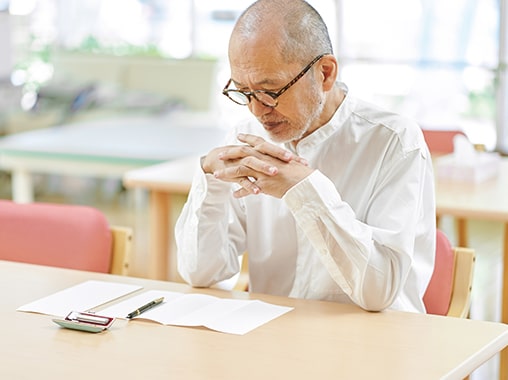生前贈与しても相続時に税金がかかる?【暦年課税】編

- 相続税申告
- 相続ワンポイントメモ
- 贈与
「基礎控除額」というのは、相続税の計算において一定額までは税金がかからないという非課税枠のことです。相続人の人数によって金額が変わります。
故人が大切にしてきた財産から税金が多く引かれてしまうのは、少しもったいない気がしますよね。
相続税対策として注目される「生前贈与」
そこで、相続税対策のひとつとしてよくあがるのが『生前贈与』です。
でも…
「贈与税がかかるんじゃないの…?」
「結局、相続の時に税金がかかるんじゃない…?」
「本当に税対策になるの…?」
そんな疑問が浮かんできて、実際に活用するには少しハードルが高く感じる方も多いのではないでしょうか。
生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」2つの制度がある
生前贈与の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。
一昨年の令和5年度には税制改正もあり、令和6年1月1日より新しいルールが適用されています。
その改正ポイントも踏まえながら、生前贈与についてできるだけ分かりやすくご紹介していきます。
「暦年課税」の仕組みとポイント
今回は生前贈与のうちのひとつ、「暦年課税」についてご説明します。
年間110万円まで非課税になる仕組み
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
年間(1月1日から12月31日の間)、110万円までは非課税
年間単位なので毎年110万贈与しても非課税です!※
110万円以下の贈与は申告不要
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※決まった金額、日にちの贈与が毎年繰り返されると「定期贈与」とみなされ、贈与税がかかる場合があります。
贈与税申告の注意点
贈与税について申告・納付をするのは、財産をもらった人(=受贈者)です。
「110万円まで」とは受贈者(もらう側)を基準として考えるので、例えば父母それぞれから100万円ずつもらい計200万円贈与された場合は、非課税枠の110万円を超えた90万円に課税されることになり、申告も必要となります。
相続時に税金がかかってくるの?
暦年課税によって贈与された財産は、死亡前の3年間(★税制改正によって年数変更)に贈与したものは相続財産に足し戻して相続税の計算をしなければなりません。
「暦年課税」の税制改正ポイント
相続財産への足し戻しの年数がこれまで死亡前3年間だったのが「死亡前7年間」へと期間が延びました。
急に期間が延びると改正前後の差が大きくなってしまうのでは…?と心配になりますよね。
足し戻しの期間は徐々に延長され将来的に7年間になるよう措置がとられているのでご安心ください!
税制改正の通り「過去7年間分の贈与が加算される」ようになるのは、
税制改正が適応された令和6年1月1日から7年が経過した令和13年1月1日以降に発生した相続ということになります。
贈与税としてすでに税金を支払っている場合、その他の場合
◆すでに贈与税を払っている場合
相続税額から支払済みの贈与税額を差引いた税額が支払うべき相続税の金額となります。
※ただし、相続税の金額が贈与税より低い場合、差額分は還付されないので注意が必要です!後に説明する「相続時精算課税」においては差額分の還付があります。
◆相続財産と贈与財産の合計金額で相続税は発生しなかった場合(基礎控除額内だった場合)
支払う税金はありません。
◆贈与者から何も相続しなかった場合(相続人ではない場合や、遺言書による遺贈がない場合)
贈与財産を相続財産に加算する必要はありません。
ここまで暦年課税について説明してきましたが、生前贈与として活用するには気を付けるべきポイントがたくさんありましたね。
相続手続サポート協会では、生前贈与や相続税対策についても無料でご相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。
次回は、「相続時精算課税」についてご紹介します!