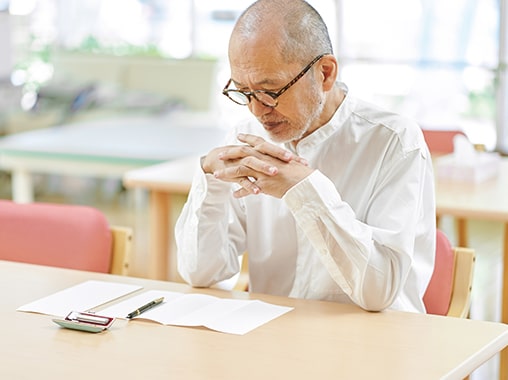あ行
相続人が複数人いて共同して相続財産を相続することを、共同相続といいます。また、この共同相続人は遺産全部につき相続分に応じて権利義務を共有するとされています。この共同相続の状態から、各相続人に遺産を分割することを遺産分割といいます。
遺贈とは、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することです。『相続』は、なんら手続きを経ることなく、当然に被相続人の財産が相続人に引継がれるのに対し、『遺贈』は遺言があることが条件となります。遺言によって財産を与えるものを遺贈者、その財産を受けるものを受遺者といいます。遺贈には『包括遺贈』と『特定遺贈』がある。
一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のこと。兄弟姉妹には遺留分がなく、直系尊属(親、祖父母)のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1になります。
婚姻によって発生する親族のことです。血族(父母、兄弟、子など)の婚姻によって発生した場合も含まれます。民法では、3親等までの姻族を親族に含めるとしています。(725条)
期限までに金銭納付が困難な場合に、一定の要件を満たすことで支払い期間を延長するものです。その場合は、延納する税額を延納期間で割り、年一回の元金均等払いをすることになります。また、担保の提供が必要であり、延納期間中には利子税(利息)が課されます。
遺言とは、ある人の生きている間の最終的な意思の決定(財産の分割方法など)を、その人が死んだ後、具体的に実行させるための方法です。 遺言には、一定の形式が必要です。
相続人が複数人いて共同して相続財産を相続することを、共同相続といいます。また、この共同相続人は遺産全部につき相続分に応じて権利義務を共有するとされています。この共同相続の状態から、各相続人に遺産を分割することを遺産分割といいます。
か行
家督相続とは、旧民法における「家」制度の下での相続です。昭和22年まではこの相続形態が続いていました。家督相続では一人の家督相続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承継するものです。旧法では、相続には戸主の地位を承継する家督相続と、戸主以外の場合の遺産相続の2種類の構成でした。
相続によって取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その代金を分割する方法です。
相続人のなかに相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者(寄与分権利者)がいる場合には、その相続人は、遺産分割の際に他の相続人に優先して、遺産から寄与分(相続財産の維持増加部分)を受けることができるというものです。注意点として、寄与分は相続人のみが認められているため、内縁の妻や長男の妻などが特別な寄与をしたとしても対象とはならないことです。また、寄与分を受けるためには、「特別の寄与」をしなければならないため、通常の家事労働や看護などでは認められません。
共同相続人全員の協議によって分割する方法のことです。通常は、遺言による指定がない場合はこの方法で行います。ただし、遺言が存在する場合であっても、共同相続人全員の協議により遺言とは異なる合意が成立した場合には、協議分割が優先します。
血のつながりのあるもののことを言います。ただし、民法では養子縁組によって発生する親族も血族と同じ扱いをしています。(727条)
相続人となるべき者が故意に被相続人を殺したり、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせたりした場合などに、法律上当然に相続人の資格を失うことをいいます。相続欠格となった者を「相続欠格者」といいます。
限定承認とは、相続人が受け継いだ資産の範囲で負債(借金など)を支払、資産(プラスの財産)を超える負債については責任を負わないという相続の方法です。相続財産の中で、借金などがプラスの財産よりも多いと思われる場合に有効となる手段です。
個別の財産について、相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法です。一般的に、この現物分割ができないときには、換価分割や代償分割をすることとなります。
証人2人以上の立会のうえで、遺言者が伝えた内容をもとに公証人が筆記し、これに署名・押印
戸籍は,人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので,日本国民について編製され,日本国籍をも公証する唯一の制度です。戸籍事務は,市区町村において処理されますが,戸籍事務が,全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。
さ行
不在者、生死不明の者(死体が確認できていない者など)を死亡したものとみなし、その者にかかわる法律関係をいったん確定させるための制度です。その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪または特別失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができるとされています。
遺言により、法定相続分と異なる共同相続人の相続分を指定することができます。これを指定分割といい、法定相続分に優先します。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自署し、これに押印することで成立します。証人や立会人は不要です。そのため、費用もかからず、遺言の存在や内容を秘密にしておくことができます。ただし、定められた様式があり、正しく記載されていない場合は無効となることもあるため注意が必要です。
除籍個人事項証明のことです。除籍原本の内容の一部を写したもので、その除籍の特定の人の証明書です。
除籍全部事項証明のことです。除籍原本の内容をそのまま全部写したもので、その除籍に記載されている全ての人の証明書です。
調停が不成立に終わった場合に、家庭裁判所の審判によって分割する方法です。審判分割は、裁判の一種であり、裁判官は「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状況及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行う(民法906)」とされています。しかし、裁判官は法定相続分に拘束され、相続人全員の合意がない限り、相続分に反する分割はでないとされています。
「税負担の公平」を確保するために、納税者の申告した内容や計算が、税法に照らして適正かどうかをチェックするものです。
「精神上の障害により判断能力が不十分であるため、法律行為をするための意思決定が困難な状態にある人」を支援し、その権利擁護を図る制度とされています。家庭裁判所より任命されるなどした成年後見人(補助人、保佐人を含む)が、このような精神に障害を持った人のために本人を代理して契約等の法律行為を行ったりします。
被相続人の財産の一切の承継を放棄することです。相続人は相続があったことを「知った日から」3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てることによって相続の放棄をすることができます。相続の放棄をすると、その者は最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。各相続人が単独ですることができます。なお、相続開始前には、相続放棄をすることはできません。もし、相続開始前に推定相続人の間で合意をしていたとしても、法的には何ら拘束力を持ちません。
た行
被相続人の死亡前に、相続人である子や兄弟姉妹が死亡していたり、相続欠格または廃除によって相続権を失っているときに、その相続人の子が代わって相続人になることを代襲相続といいます。相続人の子も亡くなっている場合は、再代襲となります。
共同相続人のうちのだれかが遺産を取得し、その代償として自己の固有の財産を他の相続人に支払う方法です。例えば、相続財産が自宅だけなど分割することが困難な場合に、自己の現金を代償金として支払う場合などがこれに該当します。
単純承認とは、被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)すべてを無条件で相続することです。単純承認には、相続人が自ら被相続人の権利・義務を承継する旨の意思表示をした場合のほか、相続人の行為や期間の経過によって、自動的に単純承認したのみなされる法定単純承認とがあります。
協議がまとまらない場合に、裁判所の調停により分割する方法です。裁判所の審判とは異なり、第三者(調停員)の仲介によって当事者が譲歩することで合意を図るものです。協議が調わないからといって、いきなり審判申し立てをすることは認められず、まず家庭裁判所へ調停を申し立てなくてはなりません。
基準となる人より前の世代の血族のことです。父母・祖父母・曾祖父母などがこれにあたります。
基準となる人よりあとの世代の血族のことです。子・孫・曾孫などがこれにあたります。
遺言者の遺産に属する特定の財産を遺贈することです。「○○市一丁目×番地×号所在の土地を遺贈する」というように具体的にそのものを特定します。ただし、遺言を書いた遺贈者が死亡したとき(遺言の効力が発生した際)に、受贈者は生存している必要があります。先に、受贈者が死亡していた場合、遺贈は無効となります。(代襲相続は生じない)
被相続人より、遺贈や生前贈与で得た財産等のことです。共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいる場合、この者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、贈与や遺贈分(特別受益)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。
な行
婚姻届を出してはいないものの、事実上の婚姻関係にある関係のことを言います。法律上の婚姻ではない内縁関係には、相続は認められません。つまり、内縁の配偶者には、相続権はありません。
成年後見制度の1つで、まだ判断能力が衰えていない人が利用する制度です。将来、認知症などの障害によって判断能力が低下したときに備えて、自ら選んだ人(任意後見人)と委任契約を結んでおき、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点で、その契約の効力が発生するというものです。
は行
被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があった場合に、「被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって」その相続権を失わせることができます。また、被相続人は遺言によって排除の意思表示をすることができ、その場合は遺言執行者が裁判所に申し立てをします。家庭裁判所の審判が必要となる点で、欠格とは異なります。
相続税を金銭で納付できない場合に、相続した一定の財産で納付することを物納といいます。物納の要件としては、「①延納によっても金銭で納付することが困難で、金銭で納付することを困難とする金額を限度とする。②申告期限までに物納申請書及び物納手続き関係書類を提出し、税務署長の許可を得ること。③その財産が物納適格財産であること。」とされています。
物納が可能とされている財産のことで、財産の範囲と順位が定められています。財産の範囲は、①「国債及び地方債」②不動産及び船舶」③社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券」④「動産」です。物納順位は、第一順位として、「国債及び地方債」「不動産及び船舶」「不動産のうち物納劣後財産」、第二順位として、「社債、株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券」「株式のうち物納劣後財産」、第三順位として、「動産」とされています。
遺言者の遺産の全部または一部を、割合をもって遺贈すること。「全財産を遺贈する。」や「全財産の4分の1を遺贈する。」のように一定の割合を示すこと。ただし、遺言を書いた遺贈者が死亡したとき(遺言の効力が発生した際)に、受贈者は生存している必要があります。先に、受贈者が死亡していた場合、遺贈は無効となります。(代襲相続は生じない)
民法で定める相続分のことです。相続人の数や続柄にもよりますが、配偶者2分の1、子は4分の1などとするものです。ただし、法定相続分があるからといって、協議の際にそれに従わなくてはならないということではありません。
ま行
本来の意味で相続財産ではないものの、相続財産と同様に人の死亡により取得される財産ということで、相続財産とみなされる財産のことです。税務ではよくでてきますが、『みなし』て課税しますよと言うものです。
形式的には配偶者や子などの名前で預金をしているものの、実質的には被相続人(亡くなった人)のもので、単に名義を借りている預金をいいます。よくあるケースで、被相続人が子どもに贈与をするつもりで、子ども名義の口座をつくり、コツコツ自分のお金を移すことがあります。これは、子どもに内緒で行っている場合には『贈与』をしたことにはなりませんので、相続税調査のときに『名義預金』(被相続人の財産)と認定されてしまう可能性があります。
や行
遺言者に代わって、遺言の内容を処理する日人のことです。遺言執行者は、遺言によって指定されることや、利害関係人の請求で家庭裁判所が選任する場合もあります。
遺言を中心とする相続関係業務を信託銀行などに任せられる制度です。遺言信託の業務としては、①公正証書の保管などを行う「遺言書管理業務」、②遺言執行者に指定された信託銀行等が、遺言の内容を実現する「遺言執行予諾業務」、③相続人からの依頼により、遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更などの手続きを行う「遺産整理業務」などがあります。
ら行
相続や遺贈により財産を取得した人が2人以上いる場合には、その相続税について互いに連帯納付の義務を負うとされています。
宅地の評価額の基準となる価格のことです。道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を表記しています。国税庁が公表し相続税・贈与税の算定基準となる財産評価基準書の路線価を相続税路線価といい、市町村が公表し固定資産税や都市計画税などの基となる固定資産税路線価があります。単に「路線価」と言った場合は、相続税路線価を指すことが多いです。