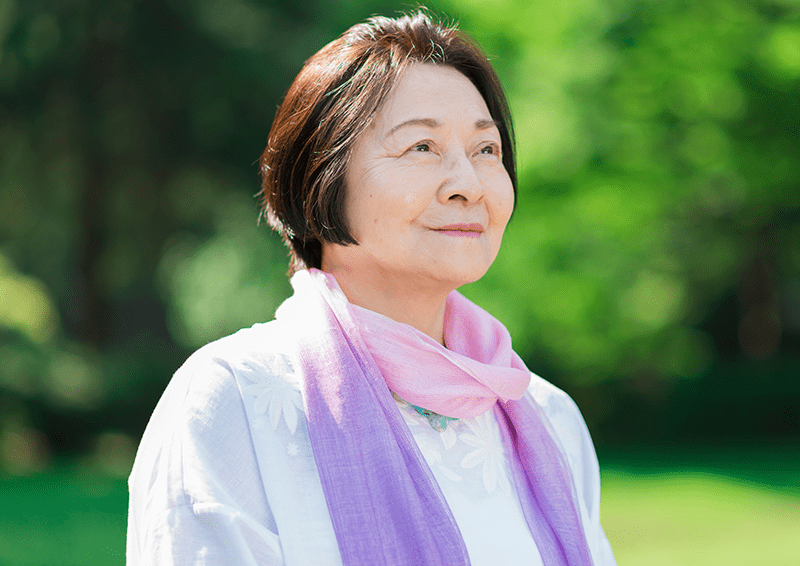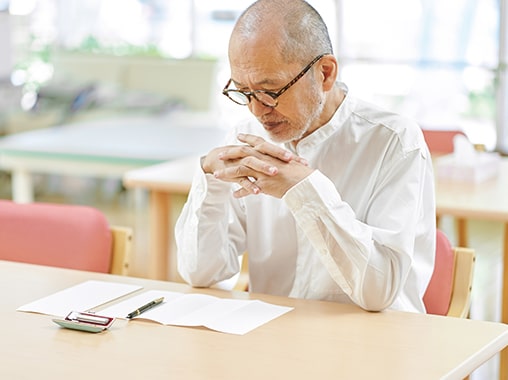郵便貯金の相続手続きとは?|ゆうちょ銀行での払戻し方法と必要書類を解説

- 相続の基本ガイド
- 預貯金・証券の相続手続き
2025.04.20
- 口座
- 銀行
相続が発生した際、ゆうちょ銀行(旧・郵便貯金)の口座も他の金融機関と同様に凍結され、相続人が手続きを行わなければ貯金を引き出すことはできません。本記事では、「郵便 貯金 相続 手続」を検討されている方に向けて、必要書類や流れ、注意点を詳しく解説します。
目次
郵便貯金は相続発生とともに凍結される
ゆうちょ銀行では、被相続人(亡くなった方)の死亡届が提出されると、口座が凍結され、預金の引き出しができなくなります。
払い戻しを受けるには、正しい相続手続きが必要です。
ゆうちょ銀行(郵便貯金)の相続手続きの流れ
ゆうちょ銀行に相続手続きを申し出る
口座のある郵便局またはゆうちょ銀行の窓口にて、相続の開始を伝えます。
その後、専用の「相続確認票」や「相続関係届書」の提出を求められます。
被相続人と相続人を確認する書類を用意
【必要書類一覧】
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または抄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺言書または遺産分割協議書(ある場合)
- ゆうちょ銀行所定の書類(相続関係届書、払戻請求書など)
- 通帳・キャッシュカード(可能であれば)
書類審査・払い戻しの手続きへ
ゆうちょ銀行での書類確認・審査が終わると、指定口座に相続金が振り込まれる形で払戻しされます。通常、2週間〜1ヶ月程度かかることが一般的です。
払戻しのための注意点
相続人全員の同意が必要
相続人が複数いる場合、原則として全員の署名・実印が必要になります。
遺産分割協議書が整っていない場合は、払戻しが保留されることもあります。
戸籍の取得が想像以上に大変なことも
「出生から死亡までの戸籍を集める」作業は、転籍や結婚歴がある場合などは複雑化します。本籍地が複数にまたがるケースでは特に要注意です。
郵便局では対応できない場合も
ゆうちょ銀行の相続手続きは、通常の郵便局(JP)ではなく、ゆうちょ銀行の本店・支店での受付が必要になることがあります。事前確認をおすすめします。
郵便貯金の相続手続きをスムーズに進めるには?
専門家のサポートを活用する
- 書類の不備を防げる
- 戸籍の取得を代行してもらえる
- 相続税や不動産の手続きも一括対応可能な場合あり
相続に不慣れな方、平日に動けない方にとって、行政書士や相続支援専門家への依頼は強い味方になります。
ゆうちょ銀行の相続手続きに困ったら専門家へ相談を
郵便貯金の相続手続きは、自分でも行うことは可能ですが、戸籍の取り寄せや遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と時間が必要になります。
当協会では、相続に関するトータルサポートを行っております。お気軽にご相談ください。
関連記事