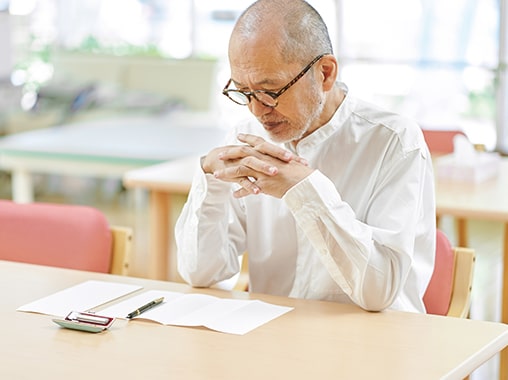生前贈与しても相続時に税金がかかる?【相続時精算課税】編

- 相続ワンポイントメモ
- 相続対策
- 贈与
前回は、税制改正によって相続財産への足し戻し期間が延長された「暦年課税」について
制度の仕組みや改正のポイントも踏まえてご紹介しました。
今回は、もうひとつの「相続時精算課税」についてみていきたいと思います。
暦年課税と比較しながら、もし贈与をする・されるならどちらの制度がよいかイメージしてみると良いかもしれません。
「相続時精算課税」の仕組みとポイント
名称の通り、生前贈与の際には非課税(非課税の贈与額には上限あり。後述)ですが、
相続の際に相続財産に足し戻して相続税の計算をするという制度です。
もちろん、足し戻して基礎控除額の金額内であれば相続税はかかりません!
贈与する人・される人の年齢と続柄
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【贈与者】原則60歳以上の父母または祖父母
【受贈者】18歳以上の子または孫 ※
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※令和4年3月31日以前の贈与については「20歳以上」。
民法改正により、成年年齢が「18歳」となったため令和4年4月1日以降の贈与については受贈者の年齢が18歳以上となりました。
「合計2500万円まで非課税」に年間110万円の非課税枠追加
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・贈与者につき、合計額2500万円までは非課税
※財産の種類や金額、贈与回数に制限なし
※非課税であっても、贈与したその年ごとに申告する必要あり!少額でも申告必須!(★税制改正)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★税制改正:令和6年1月以降の贈与から年間110万円の非課税枠が追加されました。※110万円までは申告不要!
2500万円を超えたときは?
2500万円を超えた部分に関しては、一律20%の税率がかかるので贈与税を納める必要があります。
「相続時精算課税制度」を選択したら申告を忘れずに!
「相続時精算課税制度」を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の期間で申告する必要があります。
申告を忘れてしまうと通常の贈与とみなされ、贈与税が発生してしまいます。
※「相続時精算課税」を選択すると、「暦年課税」に変更することはできません!
制度の選択は贈与者ごと
この制度は”贈与者ごと”なので、父と母からの贈与をどちらも「相続時精算課税」として申告すると、2500万円ずつ、合計5000万円まで非課税となります。
また、父からの贈与は「相続時精算課税」を選択し、母からの贈与は「暦年課税」を選択する、ということも可能です。
相続時に税金がかかるの?
相続時に『それまでの贈与額の合計』を相続財産に足し戻して基礎控除額を超えた場合に「相続税」として税金がかかってきます。
基礎控除額を超えなければ税金はかからない
相続財産と贈与財産の合計金額で相続税がかからなかった(基礎控除額を超えなかった)場合、支払う税金はありません。
非課税枠の110万円は相続財産への加算不要!
税制改正により加わった年間110万円の非課税枠については相続財産に含めなくてよいので
「相続税対策」として大いに活用できそうですね。
贈与税を支払ったときはどうなるの?
2500万円を超えた部分にはすでに贈与税を支払っていますが、この場合も “まずは”
すべての贈与額(2500万円 + 超過分)を相続財産に足し戻して相続税の計算をします。
◆相続税額が支払済みの贈与税額より大きかった場合・・・差額を支払う必要があります。
◆相続税額が支払済みの贈与税額より小さかった場合・・・差額を還付してもらうことが出来ます!
※「暦年課税」では支払済みの贈与税の金額が相続税より大きくても還付がされないので要注意!!
贈与者から何も相続しなかったら…?
相続時に財産をもらわなかったとしても、「相続時精算課税制度」を利用した場合は相続財産に足し戻さなければなりません。
受贈者が『孫』の場合の注意点!
亡くなった方の相続人ではない孫が受贈者の場合も、受け取った財産は相続財産として足し戻さなければなりませんが、相続税に「2割加算」されるというルールがあるので注意が必要です!
相続税にはもともと、被相続人の配偶者・父母・子以外の人が相続または遺贈によって相続財産を取得すると「2割加算」されるというルールがあります。
(※亡くなった方の『子』がすでに死亡しており、代襲相続人として『孫』が相続人になっている場合は2割加算はありません。)
生前贈与について二つの課税制度を見ていきましたがいかがでしたでしょうか。
「贈与」とひとことで言っても、細かなルールがいくつもあるので「相続税対策」として活用するためにはその先の相続時のことまでをシミュレーションをしておく必要がありそうですね。
相続手続サポート協会では、生前贈与や相続税対策についても無料でご相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。
今後も相続に役立つ情報を発信していきます!