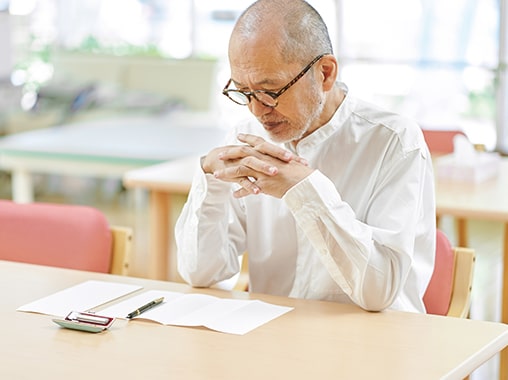相続とは?基本から手続きまでわかる相続ガイド

- 相続の基本ガイド
- 相続とは
- 相続の基本
相続は、故人の財産や権利義務を遺族が引き継ぐ重要な手続きです。しかし、法的なルールや必要な書類、手続きの流れなど、初めての方には複雑に感じられることも少なくありません。本記事では、「相続とは?」という基本から、相続人の範囲、必要な戸籍、遺産分割協議書の作成方法、さらには相続税や債務の取り扱いまで、相続に関する基礎知識をわかりやすく解説します。
相続とは?
相続の定義
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務を、法律で定められた相続人が引き継ぐことを指します。これには、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続の開始時期
相続は、被相続人が亡くなった時点で開始されます。その後、相続人は遺産の内容を確認し、相続するか放棄するかを選択します。
相続手続きは、相続税のかかる方だけの話と思っていませんか? 下記の相続流れ図を見ていただくとわかりますが、相続税がかからない人も図の中の最後の相続税申告以外は、下記の手続きをしていく必要があります。
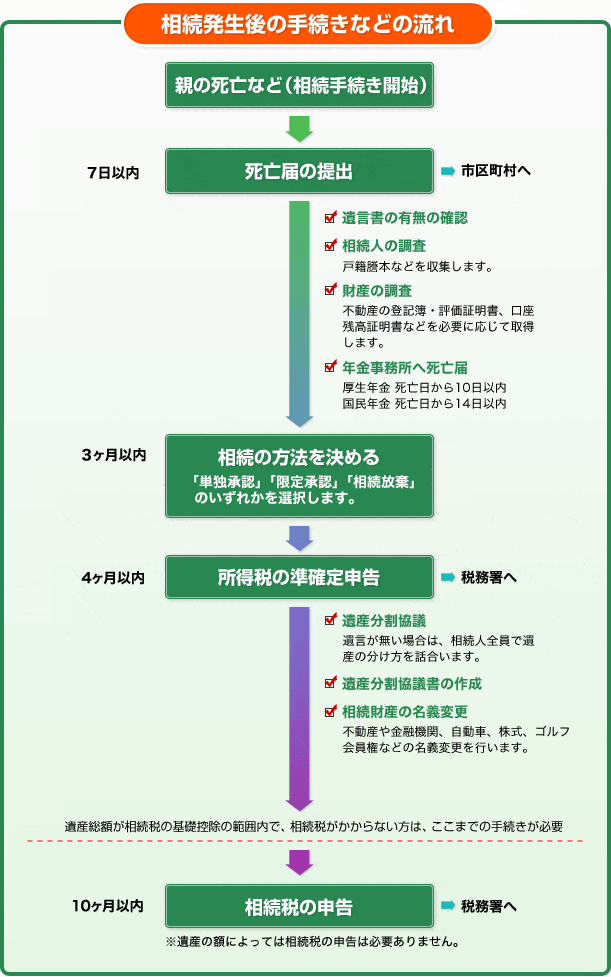
相続手続きに必要な戸籍
なぜ戸籍が必要か?
大切な方が亡くなった直後、「何をどうすればいいのかわからない」という不安を抱える方がほとんどです。ご葬儀が終わると、すぐに現実的な問題がやってきます。その最初の壁が「銀行口座の凍結」。窓口ではこう言われます。
「戸籍を持ってきてください」
相続手続きには、故人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍・印鑑証明書などが必要になります。これを聞いただけで、思わずため息が出る方も多いでしょう。
「相続人は妻と子ども2人だけだから簡単」と思っていても、故人の結婚前の本籍やご両親の戸籍が必要な場合があります。中には「前妻の子どもがいた」「養子がいた」など、戸籍を集めて初めてわかるケースも。
戸籍の収集や相続人の特定、名義変更や解約などの手続きは煩雑で専門的な知識が求められます。すべてご自身で行うのは大変です。
そんなときは、相続の専門家である当協会にお任せください。あなたの「困った!」をしっかりサポートいたします。
相続に必要な戸籍の種類
戸籍には謄本と抄本があります。
謄本とはその戸籍の全部の写しのことを言います。
抄本とは謄本の中の一部で請求のあった人の部分の写しのことです。
ようするに謄本と抄本は同じ戸籍ですが抄本は謄本の一部と理解していただければ結構です。
被相続人の戸籍謄本
被相続人の戸籍は、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を揃える必要があります。これにより、子ども(相続人)や配偶者など、誰が相続人なのかを法的に証明することができます。
相続人の戸籍抄本
相続手続きをするには、相続人全員の現在の戸籍抄本も必要です。
兄弟姉妹が相続人の場合、取得には委任状が必要になることもあるので注意しましょう。
戸籍の取得方法と注意点
戸籍取得のステップ
- 死亡の記載のある戸籍(除籍謄本)を取得
- 本籍地の役所で取得可能
- 本籍地が不明な場合は、住民票に記載された本籍地を確認
- 古い戸籍へと順にさかのぼって取得
- 結婚・転籍・市町村合併などにより戸籍が移動している場合も多く、数通の戸籍が必要になることがあります。
戸籍は本籍地でしか取得できない
戸籍は本籍地のある市区町村役場でのみ発行されます。遠方の場合は、郵送請求も可能です。
市町村合併による役所の変更に注意
近年、市町村合併の影響で役所の管轄が変更されている場合があります。必ず現在の管轄役所を調べてから請求しましょう。
「相続のため」と伝えるとスムーズな対応も
役所によっては、「相続手続きで必要」と申し出ることで、揃えるべき戸籍をまとめて案内・交付してくれることもあります。事前に電話で確認するのがおすすめです。
戸籍が必要となる相続の手続き
- 銀行、郵便局の預貯金の引き出し、口座解約
- 生命保険、損害保険の請求
- 株式の名義変更
- 自動車の名義変更
- 土地や建物の名義変更
- 電話加入権の名義変更
- 死亡退職金の請求
などなど多岐にわたります。
相続人と法定相続分
相続が発生したとき、最初に確認すべきなのが「相続人は誰か」そして「法定相続分はどのくらいか」です。
この記事では、法定相続人の範囲と相続割合の決まり方をパターン別にわかりやすく解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で定められた「相続できる人」のことです。
相続人になれるかどうかは、被相続人(亡くなった方)との続柄によって決まります。
法定相続人の順位と優先順位
相続人には優先順位があり、上位の相続人がいる場合は、下位の人は相続人になりません。
【第1順位】子(直系卑属)
- 実子・養子を含む
- 子がすでに死亡している場合は、その子(孫)が代襲相続する
【第2順位】直系尊属(父母・祖父母)
- 子がいない場合に限る
【第3順位】兄弟姉妹
- 子も直系尊属もいない場合に限る
- すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子(甥・姪)が代襲相続
配偶者は常に相続人になる
配偶者(法律上の婚姻関係にある者)は、常に相続人になります。
ただし、内縁の配偶者(籍が入っていない)は相続権がありません。
法定相続分とは?
法定相続分とは、相続人が民法上で定められた割合で遺産を分ける基準です。
遺言書がない場合、基本的にこの法定割合に従って遺産を分けることになります。
相続人と法定相続分の早見表
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子(第1順位) | 1/2 | 子が残りの1/2(複数なら等分) |
| 配偶者と直系尊属(第2順位) | 2/3 | 尊属が1/3(複数なら等分) |
| 配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 兄弟姉妹が1/4(複数なら等分) |
| 配偶者のみ | 全部 | ― |
| 子のみ | 全部 | ― |
| 直系尊属のみ | 全部 | ― |
| 兄弟姉妹のみ | 全部 | ― |
【特別なケース】非嫡出子(婚外子)の相続分
現在の民法では、婚内子と婚外子の相続分に差はありません。
【特別なケース】養子の相続分
養子は実子と同様に法定相続人になります。ただし、養子縁組の届出が必要です。
相続を放棄したい場合
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないと家庭裁判所に申し出ることです。
プラスの財産(預金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金)も一切引き継がなくなります。
相続放棄をしたいときの期限は「3か月以内」
相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。
これを「熟慮期間」といいます。
相続放棄の手続きの流れ
- 被相続人の死亡を確認
- 財産や負債の有無を調査(必要に応じて)
- 家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出
- 裁判所からの照会書に回答
- 相続放棄が受理されると「受理通知書」が届く
相続放棄に必要な主な書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍(死亡の記載があるもの)
- 申述人の戸籍
- 収入印紙(800円)
- 郵便切手(裁判所によって異なる)
相続放棄できないケース・注意点
【注意1】一度相続の意思表示をすると放棄できない
以下のような行為をすると、「相続を承認した」とみなされ、放棄ができなくなることがあります。
- 相続財産を売却・処分した
- 預金を引き出した
- 遺産分割協議に参加した
【注意2】相続放棄は取り消しできない
相続放棄が一度認められると、原則として撤回できません。
申立て前に、財産・借金の全体像を把握しておくことが大切です。
相続税の基礎知識
相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超える場合に発生します。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
債務の相続
相続では、被相続人の借金などの債務も引き継ぐことになります。債務を引き継ぎたくない場合は、相続放棄や限定承認の手続きを検討する必要があります。
遺言書とは
遺言書とは、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかを明確に示すための、法的効力を持つ文書です。
相続トラブルの予防や、想いを遺す手段として、近年注目が高まっています。
遺言書の種類
① 自筆証書遺言
- 遺言者がすべて自筆で書く
- 手軽に作成できるが、不備があると無効になるリスクがある
- 2020年からは法務局での保管制度がスタート(法的効力が高まる)
② 公正証書遺言
- 公証役場で公証人に作成してもらう方式
- 作成ミスや紛失のリスクがなく、最も安全性が高い
- 証人2人が必要
③ 秘密証書遺言
内容は秘密にできるが、手続きが複雑であまり一般的ではない
遺言書が有効となるための条件
- 法的に認められた形式であること
- 本人の意思で作成されていること
- 内容が明確で、誰に何を渡すかがはっきりしていること
遺言書でできること・できないこと
できることの例
- 財産の分け方の指定
- 特定の人への遺贈(相続人以外への財産譲渡)
- 子の認知
- 遺言執行者の指定
できないことの例
- 法律に反する内容(遺留分を無視するなど)
- 公序良俗に反する条件付きの遺贈
遺言書とは、家族を守る最後のメッセージ
- 遺言書とは、自分の意思を法律で残す大切な手段
- トラブル予防やスムーズな相続手続きのためにも有効
- 自筆証書・公正証書の違いやメリットを理解して作成を検討しましょう
遺産整理とは?
遺産整理の定義と目的
遺産整理とは、相続が発生した後に行う「財産と債務の確認」「名義変更」「分割」などの作業を総称したものです。相続人間のトラブルを防ぐため、適切かつ迅速に対応することが求められます。
相続財産の把握
特に相続税が発生しそうなときは専門家に相談されることをお勧めします。
不動産
権利証を探したり毎年送られてくる納税通知書などを確認してください。
また役場で名寄帳を取ってみたり、法務局で登記簿謄本を取ることに
よっても調べることはできます。
預貯金
ご自宅で通帳を確認してください。
そして金融機関で残高証明書を取ってください。
その他ゆうちょ銀行(郵便貯金)は口座があるか検索してもらえますので
一度確認してみてください。
その他
まずご自宅のいたるところを探してみてください。
株なら株式総会のご案内が来たり、保険なら証券や年末調整の案内が
あったりします。また銀行などで貸金庫を借りられていたり、
信託銀行へ信託してあったりもします。
心当たりのあるところへお問い合わせ下さい。
財産調査
当協会では遺産整理をし財産目録の作成を行っております。
上記のような情報をお客様からいただき、作成します。
財産の情報収集でご不明な点があれば、きめこまかく支援させて
いただいておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割方法
遺産分割方法は、被相続人が残した財産をどのように相続人で分けるかを決定する重要な手続きです。
現物分割
Aには不動産を、Bには預貯金を、Cには現金をといったように
遺産をそのままの形で分割する方法です。これが一般的です。
代償分割
Aがすべての遺産を相続する代わりに、B,Cにはその代償として
各500万円支払う、という方法です。
換価分割
遺産を売却してその売却代金を分配する方法です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意することです。この合意内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書の作成が必要な理由
なぜ協議書が必要なのか?
被相続人が遺言を残していない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その結果を「遺産分割協議書」として文書化する必要があります。
この協議書がなければ、相続財産の名義変更や預金の解約手続きが進められません。
相続人が一人でも作成が必要?
相続人が複数いる場合に必要です。相続人が1人のみの場合は、協議書の作成は不要です。
遺産分割協議書の効力と使い道
- 預金の解約、証券口座の名義変更、不動産の登記変更に使用されます
- 原則、相続人全員が同じ書面に署名・押印
- 印鑑証明書は「協議成立日から3ヶ月以内」のものが望ましいとされています
遺産分割協議書のポイント
- 遺産分割協議書には特に様式はありません。
後日の紛争を避けるための証拠として、また諸手続をするために作成するものです。 - 諸手続に使う場合は実印で押印し相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
- 日付は西暦でも和暦でも構いません。
- 遺産は特定できるよう記載します。
- 住所は住民票どおりに記載します。
- 今後遺産が見つかった場合の分配を決めておいたほうがよいでしょう。
- 分割協議書が複数枚になった時は割り印をします。
- 未成年者や認知症などで判断能力がない方がいる場合は、特別代理人や成年後見人を裁判所に申立をして選任しなければ遺産分割はできません。また行方不明の相続人がいる場合も裁判上の手続きが必要です。
- 有効にされた遺産分割のやり直しは、贈与税の対象になる可能性があるので注意が必要です。
債務(借金)も相続される?
相続というと、財産を受け継ぐ「プラスの財産」ばかりに目が行きがちですが、実際には借金などの「マイナスの財産(債務)」も相続の対象となります。
マイナスの財産とは?
- 借金(消費者金融・銀行ローンなど)
- クレジットカードの未払い分
- 損害賠償責任
- 連帯保証人としての債務 など
銀行預金の解約と手続き
家族が亡くなったあと、避けて通れないのが「銀行預金の解約手続き」です。
被相続人(亡くなった方)の銀行口座は、死亡の事実が判明した時点で凍結され、遺族が勝手に引き出すことはできません。
銀行口座は凍結される?
被相続人が亡くなると、金融機関に死亡が伝わった時点でその口座は凍結されます。これにより、引き出しや振込などの取引が一時的にできなくなります。
預金の引き出しや名義変更を行うには、相続人全員による同意が必要で、正式な手続きを踏まなければなりません。
銀行預金の解約手続きの基本的な流れ
銀行ごとに多少異なりますが、以下が一般的な手続きの流れです。
ステップ1:金融機関へ連絡・必要書類の確認
- 口座のある銀行に死亡の事実を伝え、必要書類の案内を受けます。
ステップ2:戸籍や書類の収集
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍・印鑑証明書
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 相続人の本人確認書類
ステップ3:銀行での解約申請
- 各銀行指定の「相続手続依頼書」に記入し、必要書類とともに提出します。
ステップ4:審査後、口座解約・払戻し
- 銀行側の審査を経て、解約・払戻しが行われます。
銀行預金の解約に必要な書類一覧
共通で必要となる書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡までのすべて)
- 相続人全員の戸籍謄本または抄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印)または有効な遺言書
- 各銀行所定の相続手続依頼書
注意:銀行によって異なるケースあり
同じ銀行でも支店によって案内が異なることがあります。事前に支店ごとに確認することが大切です。
相続の専門家に相談するメリット
相続は専門知識を要する手続きが多く、相続人間でのトラブルにも発展しかねません。相続に詳しい専門家(司法書士・税理士・行政書士・弁護士)に相談することで、正確かつスムーズに手続きを進めることができます。
こんな方は専門家へ相談を
- 相続人が多数いて意見が分かれている
- 財産の内容が複雑(株式、不動産、未登記物件など)
- 相続税の申告が必要
- 相続放棄・限定承認を検討したい
郵便貯金の解約手続き
郵便貯金も必要書類や手続の仕方が決まっています。
詳しくは別の記事にまとめていますので、ご参考にしてください。
JA貯金の解約手続き
各JAによって、必要書類や手続の仕方が多少違います。
詳しくは別の記事にまとめていますので、ご参考にしてください。
まとめ|相続の基本を押さえて、冷静な対応を
相続は突然訪れますが、事前に基本を知っておくことで、慌てずに対応することが可能です。相続人の範囲、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、銀行預金の手続き、相続税の考慮など、1つ1つ丁寧に対応していきましょう。