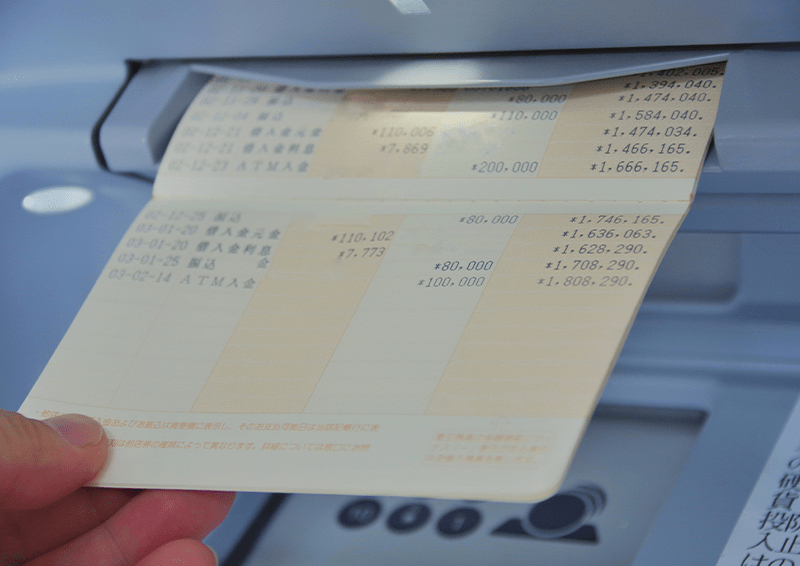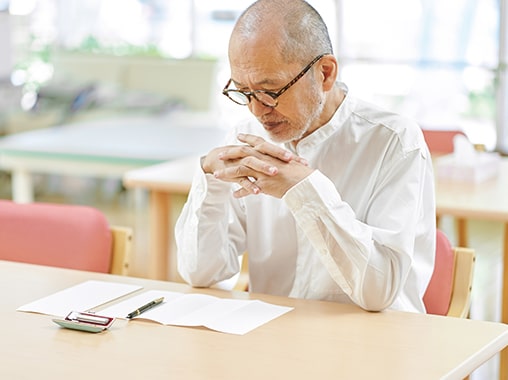個人向け国債は死亡時にどうなる?相続・名義変更・解約の注意点を解説

- 預貯金・証券の相続手続き
2025.04.16
- 個人向け国債
個人向け国債は、安定した利子収入が得られる金融商品として人気ですが、保有者が死亡した場合の手続きや扱いについては、あまり知られていません。
相続の場面では、損をしないための知識と準備が必要です。この記事では、「個人向け国債 死亡時」に知っておくべき情報を解説します。
目次
個人向け国債の死亡時の取り扱いとは?
死亡したら自動的に解約される?
個人向け国債は、名義人が死亡した時点で解約されるわけではありません。
相続人が所定の手続きを行い、「名義変更」や「相続解約」をする必要があります。
名義変更と解約の選択肢
相続人がそのまま国債を引き継ぐ場合は「名義変更」、現金化する場合は「相続解約」を選択します。
どちらを選ぶかで、受け取れる金額やタイミングが変わるため注意が必要です。
相続時に損をしないためのポイント
中途解約による損失に注意
国債を相続解約する場合、金利の一部(直近1年分など)が差し引かれる可能性があります。
「名義変更して満期まで保有」した方が、結果的に有利なケースもあります。
手続きが遅れると利子を受け取れないことも
死亡の届け出や手続きが遅れると、利子の受け取りができなくなる期間が生じる可能性があります。
特に証券会社や金融機関での手続きには時間がかかることがあるため、早めの対応が重要です。
個人向け国債の相続手続きの流れ
- 死亡の届け出を金融機関へ提出
- 相続人の確定(戸籍謄本や遺産分割協議書の準備)
- 名義変更または相続解約の選択
- 必要書類を提出して手続き完了
※機関によって必要書類は異なるため、事前確認が必要です
国債を相続する際の注意点
誰が相続するかでトラブルになるケースも
国債は現金と異なり、分けにくい資産のひとつです。遺産分割協議で揉めることがないよう、事前に意向を伝えておくことが大切です。
相続税の対象になる
個人向け国債も、もちろん相続税の課税対象です。評価額は、死亡日時点の時価で計算されます。
まとめ|個人向け国債は死亡時の対応が重要です
個人向け国債は、死亡後の扱いによって損をする可能性がある金融商品です。
相続人がスムーズに手続きできるように、遺言や生前の情報共有が重要になります。
名義変更か解約かで受け取る額も変わってくるため、判断は慎重に行いましょう。
相続や手続きで不安がある方は、ぜひ当協会にお任せください。
関連記事